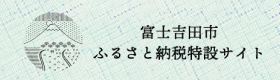本文
令和7年度 インフルエンザ予防接種
富士吉田市では下記の方に接種費用の一部助成を行います。
予防接種を受ける前にお読みください
季節性インフルエンザ予防接種が10月1日から始まります。この予防接種は、インフルエンザに対して、個人の重症化予防を目的としていますので、発症を必ず防ぐわけではありません。接種義務はありませんので、効果と副反応のリスクを正しく理解し、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。
詳しい注意事項について→「予防接種に関する説明」 [PDFファイル/1.56MB]
対象者と助成内容
(1)高齢者インフルエンザ予防接種【定期接種】
対象者
・65歳以上の方
・60歳から65歳未満の慢性高度心臓・腎臓・呼吸器・免疫不全の方(身体障害者手帳1級相当)
助成額
2,500円(接種費用から助成額2,500円を差し引いた自己負担あり)
持ち物
水色の予診票・本人確認書類・自己負担金
※接種日時点で富士吉田市に住民登録のある方に限ります。
※予診票は対象者のみ送付しています。
※インフルエンザ(水色)と新型コロナ(黄色)の予診票が1つの封筒にまとまって届きます。
※今年度65歳を迎える方は、誕生日前日から接種可能です。誕生日の直前に予診票が届きます。
※予診票のない方は接種できませんので、必ずお持ちください。
※対象者ではない方の接種は、全額自己負担となります。
※接種にかかる費用は直接医療機関へお支払いください。
(2)身障者インフルエンザ予防接種【任意接種】
対象者
18歳(高校生相当を含まない)から60歳未満の慢性高度心臓・腎臓・呼吸器・免疫不全の方(身体障害者手帳1級相当)
助成額
2,500円(接種費用から助成額2,500円を差し引いた自己負担あり)
持ち物
白色の予診票・本人確認書類・自己負担金
※接種日時点で富士吉田市に住民登録のある方に限ります。
※予診票は対象者のみ送付しています。
※予診票のない方は接種できませんので、必ずお持ちください。
※対象者ではない方の接種は、全額自己負担となります。
※接種にかかる費用は直接医療機関へお支払いください。
(3)こどもインフルエンザ予防接種【任意接種】
- 不活化ワクチン(注射)
【1回目】
対象者
生後6カ月~18歳(高校3年生相当)
助成額
2,500円(接種費用から助成額2,500円を差し引いた自己負担あり)
持ち物
本人確認書類・自己負担金
【2回目】
対象者
生後6カ月~15歳(中学3年生)
※ただし、13歳以上は基礎疾患等により医師が必要と認める者のみ
助成額
1,500円(接種費用から助成額1,500円を差し引いた自己負担あり)
持ち物
本人確認書類・自己負担金
- 経鼻ワクチン(点鼻)
【1回】
対象者
2歳~18歳(高校3年生相当)助成額
2,500円(接種費用から助成額2,500円を差し引いた自己負担あり)持ち物
本人確認書類・自己負担金
こどもを対象とするインフルエンザ予防接種では、接種を受ける医療機関にある予診票を使用してください。
※接種日時点で富士吉田市に住民登録のある方に限ります。
※対象者ではない方の接種は、全額自己負担となります。
※接種にかかる費用は直接医療機関へお支払いください。
実施期間
令和7年10月1日(火)から令和8年2月28日(土)の間、1人1回限り
※予約開始日・接種可能日については、ワクチンの流通状況等により各医療機関によって異なります。
予約方法・実施医療機関
医療機関へ直接ご予約ください。
実施医療機関について→R7年度インフル・新型コロナ予防接種実施医療機関一覧 [PDFファイル/458KB]
※やむを得ず実施医療機関以外での接種を希望される方は、事前に手続き(償還払い・予防接種委託契約など)が必要になる場合があります。
接種を受ける前に、健康長寿課 健康推進担当までお問い合わせください。
新型コロナワクチン接種の接種間隔について
新型コロナワクチンとインフルエンザを含む他のワクチンとの同時接種は医師が特に必要と認めた場合に可能です。
また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。副反応による健康被害は、極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
(1)予防接種法に基づく予防接種(定期の予防接種・臨時の予防接種)
健康被害が接種を受けたものであると厚生労働省大臣が認定したときに、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度による救済給付を受けることができます。健康長寿課 健康推進担当までお問い合わせください。
詳細はこちら(厚労省HP・予防接種健康被害救済制度について)<外部リンク>
(2)任意接種(接種を受ける者が任意で行う接種)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となり、医薬品副作用被害救済制度の対象になる場合があります。(予防接種法に基づく予防接種ではないため、「(1)予防接種健康被害救済制度」の対象にはなりません。)
給付の請求は、副作用によって健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。
※予防接種法に定期接種として定められた予防接種の種類であっても、定められた対象期間を外れて接種した場合は、任意接種となります。
詳細は、こちら(医薬品副作用被害救済制度(PMDA))<外部リンク>をご確認ください。