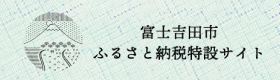本文
登録有形文化財
市内にある登録有形文化財13件をご紹介します。
鹿留発電所うそぶき放水路吐口部
種別:登録有形文化財
名称:ししどめはつでんしょうそぶきほうすいろとくちぶ
指定年月日:平成9年1月5日
所在地:富士吉田市旭5-2457-1、5-2462-1、5-4636-1
所有者:東京電力株式会社
河口湖の水を宮川へと導き,下流で発電の用に供するための水路です。斜面の中腹に石造の坑口を設け、斜面を開渠で流下させる構成です。呑口部と同様に石積みの構法等に時代の特徴が現れており、また年月を経て周囲の景観に溶け込んでいます。
上文司家住宅主屋
種別:登録有形文化財
名称:じょうもんじけじゅうたくしゅおく
指定年月日:平成29年10月27日
所在地:富士吉田市上吉田4-269
所有者:個人
上文司家は上吉田の御師の家で、上吉田の町が成立した1572年から続く家筋です。敷地は縦に細長く、本通りからタツミチとよぶ通路を入り、長屋門をくぐると主屋があります。主屋には横方向に5室が並び、富士講の人々を迎える客間となっていました。このうちの1室が富士山の祭神を祀る御神前となっています。この主屋の建築年代は幕末から明治初期と推定されます。
現在、個人の住宅となっており、敷地及び建造物は一般公開されていません。
原家住宅主屋
種別:登録有形文化財
名称:はらけじゅうたくしゅおく
指定年月日:平成29年10月27日
所在地:富士吉田市上吉田6-162
所有者:個人
原家は上吉田の御師の家で、屋号は「竹谷(たけや)」といい、上吉田の町が成立した1572年から続く家筋です。敷地は縦に細長く、本通りからタツミチとよぶ通路を入り、中門をくぐると主屋があります。主屋の左手には式台をもつ玄関、右手にはナカノクチとよばれる入口があり、それぞれの奥に2部屋ずつあり、富士講の人々を迎える部屋となっていたようです。奥にある渡り廊下を進むと富士山の祭神を祀る御神前があります。
高尾家住宅(絹屋町織物市場)
種別:登録有形文化財
名称:たかおけじゅうたく(きぬやまちおりものいちば)
指定年月日:平成29年10月27日
所在地:富士吉田市下吉田2-431
所有者:個人
高尾家住宅は、織物の市が開かれた下吉田の絹屋町にあります。高尾家は問屋を営んでおり、糸を仕入れ、織賃を払って機屋に布を織らせ、それを大阪や東京の問屋に販売していました。住宅は住居部分と店舗部分に分かれ、住居部分は1925年に建てられ、1938年に店舗部分を増築したといいます。
冨士山元祠

種別:登録有形文化財
名称:ふじさんげんし
指定年月日:令和3年10月14日
所在地:富士吉田市上吉田字浅間下1-1
所有者:宗教法人扶桑教元祠
宗教法人扶桑教元祠の神殿及び拝殿です。北口本宮冨士浅間神社の西側に隣接して建ちます。北を正面とし、平入りで唐破風向拝が付きます。内部に入ると中央が板敷の土間となっており、床は板敷と薄縁敷で、奥に進むと畳敷となり、正面三間の神殿があります。
扶桑教は、上吉田の御師や各地の富士講を組織して、1873(明治6)年に政府から認可を受けた宗教教団です。冨士山元祠は、扶桑教立教の地に1876(明治9)年に建てられたものです。建立にあたっては、上吉田の大工や信徒など200名以上が手弁当で作業にあたり、部材は地元の木を使い、17日後には上棟式を行っています。
冨士山元祠は、当初の姿をよく残すだけでなく、富士登山に向かう富士講が内部に土足で入り祈祷を受けることができるようになっているなど、富士山信仰と富士講の歴史と文化を知ることができる貴重な建造物です。
大鴈丸家住宅主屋

種別:登録有形文化財
名称:おおがんまるけじゅうたくおもや
指定年月日:令和6年3月6日
所在地:富士吉田市上吉田7-636
所有者:個人
大鴈丸家は、上吉田の御師の家で、上吉田の町が成立した元亀3年(1572)から続く家筋です。敷地は縦に細長く、表通りからタツミチと呼ぶ通路に入り水路を渡ると主屋があります。
主屋は、平屋建切妻造平入鉄板葺で西面して建ち、手前左手(北面)に角屋(つのや)の台所を延ばします。正面中央に式台(しきだい)玄関を設け、その奥に8畳、10畳の座敷が4部屋あり、うち1部屋は床・棚・付書院を備えるなど、富士講が宿泊した当時の様相を留めます。なお、屋敷の奥には御神前がありましたが、昭和40年(1965)に民宿を始めた際に撤去されました。正面左手の内玄関を入るとホールに改装されていますが、かつては家族の居住空間であったと考えられます。
冨野家住宅主屋

種別:登録有形文化財
名称:とみのけじゅうたくおもや
指定年月日:令和6年3月6日
所在地:富士吉田市上吉田4-277
所有者:個人
冨野家は御師の家で、元の姓は小澤姓で屋号を注連屋(しめや)といいます。敷地は縦に細長く、表通りからタツミチと呼ぶ通路を入り、水路をわたり中門をくぐると主屋があります。
主屋は、平屋建切妻造妻入鉄板葺で東面して建ち、手前右手(北東)に角屋(つのや)の台所を延ばします。正面中央に式台(しきだい)玄関を設け、奥に向かって3部屋を並べ、鍵の手に折れて御神前の間と御神前があります。式台玄関右手には中の玄関があり、奥に2部屋あり、居住空間となっています。一間ごとに柱が入るなど古式な造りであり、18世紀までさかのぼる可能性もあります。
中門は、簡素ながらも御師住宅の風格ある構えをつくる門です。
冨野家住宅中門

種別:登録有形文化財
名称:とみのけじゅうたくなかもん
指定年月日:令和6年3月6日
所在地:富士吉田市上吉田4-277
所有者:個人
冨野家は御師の家で、元の姓は小澤姓で屋号を注連屋(しめや)といいます。敷地は縦に細長く、表通りからタツミチと呼ぶ通路を入り、水路をわたり中門をくぐると主屋があります。
旧料亭角田主屋

種別:登録有形文化財
名称:きゅうりょうていかくだおもや
指定年月日:令和6年3月6日
所在地:富士吉田市下吉田3-827-3他
所有者:個人
下吉田の月江寺参道に西面する旧料亭の主屋です。昭和3年(1928)に料亭として建てられ、地場産業である織物の関係者でにぎわいましたが、第2次世界大戦中の昭和18年(1943)に廃業し、その後、角田医院(併用住宅)として昭和61年(1986)まで使用されました。
主屋は二階建入母屋造平入桟瓦葺で正面に唐破風造の玄関を付し、2階中央に軒唐破風に千鳥破風を重ね、垂木は扇垂木とし、戸袋に素晴らしい彫刻を施し、腰組付高欄を廻らした華やかな外観です。座敷は出節の極太床柱、折上格天井とし、昭和初期の豪壮な気風を示す料亭建築です。
旧料亭角田脇門

種別:登録有形文化財
名称:きゅうりょうていかくだわきもん
指定年月日:令和6年3月6日
所在地:富士吉田市下吉田3-827-3
所有者:個人
下吉田の月江寺参道に西面する旧料亭の脇門です。主屋の西に位置し、月江寺参道に面して建つ一間一戸の腕木門です。
屋根は切妻造鉄板葺で、欄間に梅の透彫を入れて飾るなど、主屋とともに、料亭の華やかさを伝える脇門です。
小澤家住宅主屋

種別:登録有形文化財
名称:こざわけじゅうたくおもや
指定年月日:令和7年3月13日
所在地:富士吉田市上吉田6-132
所有者:個人
小澤家は、上吉田の御師の家で、上吉田の町が成立した元亀3年(1572)から続く家筋です。屋号を筒屋(づづや)といいます。敷地は縦に細長く、表通りからタツミチと呼ぶ通路を進み、中門をくぐり水路を渡ると主屋があります。
主屋は平屋建切妻造妻入、屋根は鉄板葺で東面して建ち、北に土間と台所や家族が居住する部屋があり、南に客間として八畳と十二畳の座敷を2部屋並べ、中央に玄関を構えます。奥にある主座敷は床・棚・菱格子欄間の付書院を備え、2階にも客間が2部屋あります。建築年代は明治前期と推定されます。裏庭には御神前の建物が独立して建ち、昭和52年(1977)に改修されていますが、御神灯には天保6年(1835)の銘があります。
間取りなど御師住宅の様相をよく留めており、現在も富士講を迎え入れています。
旧宮下家住宅(柏屋)米蔵

種別:登録有形文化財
名称:きゅうみやしたけじゅうたくかしわやこめぐら
指定年月日:令和7年3月13日
所在地:富士吉田市上吉田4-264
所有者:個人
宮下家は、富士山の登山口である上吉田の中央西側に位置します。屋号は柏屋です。雑貨商を営んだ商家で、夏には富士登山者へ登山用品などを販売しました。また、農業と養蚕を営み、毎年収穫される米を米蔵に保管してきました。
米蔵は敷地西寄りに建ちますが、かつては表通りに面した東側に主屋がありました。造りは2階建切妻造平入で、屋根は鉄板葺で外壁は漆喰塗仕上げです。東に戸口を開けて下屋を付し、右手に物置が付属します。各階1室の板敷で、内壁は厚さ約82ミリの板を積んだ井籠蔵です。屋根は置屋根のため、天井と屋根の間に大きな空間があります。戸口は、観音開きの扉が合わさる部分に段をつけて漆喰を塗る掛子塗にするなど丁寧な造りとなっています。建築年代は明治前期と推定されます。
山口家住宅(𠮷田屋)表門
種別:登録有形文化財
名称:やまぐちけじゅうたくよしだやおもてもん
指定年月日:令和7年11月17日
所在地:富士吉田市上吉田1-3843-1
所有者:個人
中曽根の本町通り東側にある山口家(屋号:𠮷田屋)の表門です。山口家は、明治時代初めに開業した𠮷田屋旅館を約20年前まで営んできました。この表門は、旅館の門として明治時代に建てられたものです。構造形式は、一間薬医門・切妻造瓦棒銅板葺で、重厚な板戸を両開きに吊ります。軸部は木太く質実なつくりで、富士みちのランドマークとなる門です。