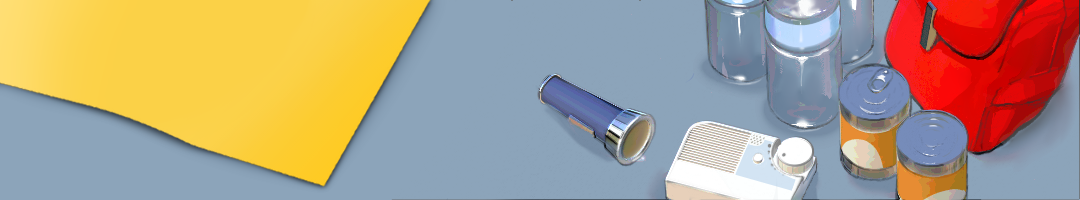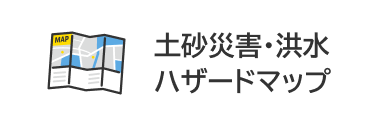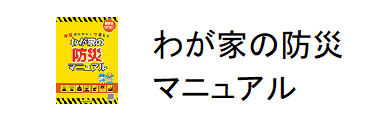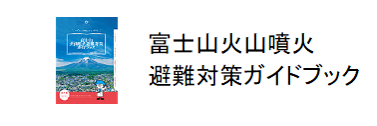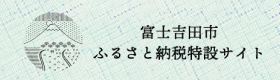本文
防災思想の普及啓発
1.防災出前講座
当市では、防災に関する出張講座を実施しています。団体や組織に関係なく、10人以上の市民の方の集まりであれば、ご都合の良い時間に安全対策課の職員が伺います。
現在講座の内容は、地震を中心としたものですが、ご依頼に応じて風水害や火山防災の話しを織り交ぜることも出来ますので当課防災担当までご相談下さい。
講座会場:ご依頼者側でお願い致します。
講義時間:ご相談にて決定。※ある程度の調整は出来ますが、最低30分以上でお願いします。
講義内容:ご相談にて決定。※ご要望が無ければ、地震のお話を中心にさせて頂きます。
講義の進め方:プロジェクターとスライドを用いての説明(パンフレットや資料も配布)。
対応可能な日時:平日(~21時00分)、土日祝祭日(9時00分~21時00分)
※ただし、他業務との関係でご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご承知おき下さい。
2.富士吉田市における主な災害履歴(富士吉田市史及び地域防災計画より抜粋)
火災
|
発生年月日 |
内容 |
|
|---|---|---|
|
昭和27年4月17日 |
下吉田新屋敷(現曙町)、32棟全半焼 |
|
|
昭和28年2月28日 |
下吉田新屋敷(現曙町)、郵便局等10棟全焼 |
|
|
昭和30年12月20日 |
吉田高等学校火災 |
|
|
昭和32年8月8日 |
下吉田駅前火災、16棟全半焼 |
|
|
昭和36年1月17日 |
下吉田月江寺駅通り火災、9世帯6棟全焼 |
|
|
昭和39年12月3日 |
下吉田宮下町、8棟全半焼 |
|
|
昭和40年4月2日 |
大明見、7棟全半焼 |
|
|
昭和45年2月26日 |
下吉田、映画館焼失 |
|
|
昭和46年12月2日 |
下吉田中央区、百貨店火災 |
|
|
昭和48年12月24日 |
富士急ハイランド本館焼失 |
|
|
昭和52年10月19日 |
上吉田中曽根、10棟全半焼 |
|
雪代災害
|
発生年月日 |
内容 |
|
|---|---|---|
|
昭和36年3月25日 |
昭和に入って二度目の雪代災害(一度目は昭和13年)で、二十三年振りの大きな雪代災害となった。 |
|
風水害
|
発生年月日 |
内容 |
|
|---|---|---|
|
昭和34年8月14日 |
富士吉田市全域、被災総数112世帯、住宅全壊8戸、半壊104戸 |
|
|
昭和34年9月26日 |
富士吉田市全域、被災総数450世帯、住宅全壊5戸、半壊15戸、一部損壊430戸 |
|
|
昭和41年9月26日 |
富士吉田市全域、重傷者2名、軽傷者8名、住宅全壊225戸、半壊34戸、床上浸水43戸、床下浸水18戸、一部損壊320戸 |
|
|
昭和58年8月16日 |
新倉地区、床上浸水67戸、床下浸水78戸、道路決壊3箇所、山崩れ5箇所 |
|
|
平成3年8月20日 |
向原地区、全壊1戸、半壊8戸、床上浸水76戸、床下浸水103戸 |
|
地震災害
3.家具の固定について
平成7年1月に発生した阪神淡路大震災(兵庫県南部地震)では、6,400名を超える人たちが犠牲となりました。そして、その亡くなった方々の多くは、倒壊した家屋や家具の下敷きによる圧死、窒息死でした。また、骨折などのケガの原因も家具の転倒によるものが大変多かったと言われています。
今一度、自宅や職場における自分の周りにある家具やキャビネットなどの配置状況をご確認頂き、転倒の危険性があるものは配置場所の変更や固定金具の設置をお願い致します。
家具などの固定は、個人で行える防災対策のうち、非常に簡易で効果の高い対策のひとつです。発災の瞬間は誰の手も借りられません。地震があったとき、まずケガなどをしない環境づくりが必要です。
最後に、一昨年の新潟県中越地震ではプロパンガスの容器が転倒するケースも報告されています。プロパンガスをご利用されているお宅では、この容器の固定状況にもご注意ください。
4.家族防災会議を開きましょう
地震などの災害が発生したとき、家族全員が自宅に居るとは限りません(仕事・学校・旅行・etc)。もし、家族がそれぞれ違った場所に居るとき大きな地震が起こったら、まず心配になるのは家族の安否だと思います。携帯電話などの連絡手段も使えず、道も寸断されているといった状況では家族の状況を知るのは容易なことではありません。家に戻っても誰も居ない、どこへ避難したか分からない(避難所・親族の家・友人宅など)。また、そうした状況では自宅付近が危険な状況になっていても、家族が居るかも知れないと思い危険を承知で自宅に行き二次災害に遭ってしまうことも考えられます。
こうしたことにならないように是非ご家族全員で防災会議を開いて頂き、以下のことについては少なくとも話し合ってもらいたいと思います。
- 避難先(一時集合場所、市指定避難場所、親族宅、その他)を決めておく。
- 連絡手段の確保(災害伝言ダイヤル171や災害用伝言板の利用など)
- 備蓄の検討実施(オムツ・ミルク・常備薬など)
おまけ
遠方の親類縁者を活用する方法
災害時における電話の通信規制は、基本的に被災していない地域から被災した地域へのものに対して行われます。これは逆に言えば、被災した地域から被災していない地域への電話は規制を受けていないとなります。無論、被災地域の電話線や交換機などが断線や故障といった物理的なものにより使えない場合には復旧を待つより他にありません。
ですが、単に通信規制により家族との連絡が取りづらいといったときには、遠方の親類縁者の人に連絡中継基地になってもらう方法もあります。ただ、これには事前に家族同士で話し合い誰にそれをお願いするか決めておかなければいけません。
5.地震だ!!発災直後の取るべき行動
誰でも大きな地震に見舞われたら、大なり小なり動揺してしまい適切な行動を取るのは難しいと思います。ただ、そんなときでも適切な行動を知っているのと知らないとでは、その後の行動に自ずと違いが出てきます。以下のことを参考にして頂き、発災直後の「自分の行動指針」を決めておくことは大変重要です。
自宅で地震にあった場合
|
発生年月日 |
内容 |
|
|---|---|---|
|
大正12年9月1日 |
関東大地震、富士吉田市全域、瑞穂村(現下吉田)全半壊35戸、福地村(現上吉田)全半壊33戸、明見村全半壊489戸 |
|
|
時間経過 |
取るべき行動 |
備考 |
|---|---|---|
|
地震発生 |
あわてない、まずは身体防護(特に頭部の保護)!! |
|
|
|
↓ |
|
|
~1分 |
揺れが落ちついてきたら、火を消す(コンロ・ストーブ)、窓やドアを開ける。 |
揺れている最中、無理に火を消そうとしない。 |
|
|
↓ |
|
|
1分~2分 |
揺れがおさまったら、家族の状況確認、火元の確認、靴やヘルメットの着用。 |
|
|
|
↓ |
|
|
2分~3分 |
余震に注意しながら、近所への声かけ(火災発生の有無、ガス漏れや漏電の確認)を行う。 |
自治会で一時集合場所が決まっている場合、一度そこへ集まり自分たちの安否や自宅周辺の状況を報告し、救出作業などが必要な場合、ここで協力要請を行う。 |
|
|
↓ |
|
|
5分 |
ラジオや防災無線で正しい情報を取得する。 |
|
|
|
↓ |
|
|
10分 |
近隣者同士で助け合いながら、消火・救出活動の従事。 |
6.正常化の偏見(normalcy bias)
これは、異常な事態が発生しても、危険な状態であるという認識がなかなか持てない(危険を無視する・無視したい)という人の心理を表現したものです。
顕著な事例として、2003年2月に発生した韓国の地下鉄列車放火事件があります。このとき、車内は火災により煙が充満していたにもかかわらず、多くの人がそれを危険なものと認識できず(「まさか列車内に放火され火災になっている」とは誰も考えない。)、逃げ遅れてしまいました。結果、300人を超す死傷者を出す大惨事となったのです。日本でも、例えば2003年5月に発生した宮城県沖の地震では津波警報が出たにもかかわらず、多くの人が避難しなかったということがありました。この地域は、過去地震や津波で大きな被害を出しており、そのための教育や人々の意識がもともと高いと思われているところです。
災害現場でのインタビューでよく聞かれる言葉に「まさか、自分がこんな目にあうとは思わなかった。」、「ここに何十年も住んでいて初めての経験だ。」、「こんなことなら、○○しとけば良かった。」といったものがあります。
確かに、災害や事故、事件というのはそうそう自分の身に降りかかるものではありません。仮に何か危険なサイン(気象警報・避難勧告など)があっても、日常生活の経験(危険な目にあったことの無い)から事態を楽観視したり、過去の被災経験から「昔の水害では、ここは被害を受けなかったから今回も大丈夫だ。」と考えたりしがちです。
災害はいつ何時、どんな形で私たちを襲うか分かりません。テレビやラジオ、同報無線などから「気象警報」が放送されたときには、雨戸の戸締り、飛散しそうな物の固定などの事前対策を行い避難時における携行品の確認。そして、「避難勧告」が出されたときや危険かも知れないと判断される状況があったときには、正常化の偏見にとらわれず「迷わず逃げる。」ことが自分や家族を守ることにつながります。
7.防災気象情報
防災気象情報とは、以下の基準に基づいて気象台より発表されるものです。この情報は、TVやラジオのほか同報無線(警報発表時)でも放送されます。また、気象台のホームページから確認することも出来ます。
注意報
大雨、大雪などによって災害が起こる恐れがあると想定される場合、その旨を注意し発表されます。
|
種類 |
発表基準 |
|---|---|
|
強風 |
12m/s(ただし甲府地方気象台の観測値では14m/s) |
|
風雪 |
12m/s(ただし甲府地方気象台の観測値では14m/s)、雪を伴う場合 |
|
大雨 |
1時間雨量 盆地20mm以上、山地40mm以上 |
|
3時間雨量 盆地40mm以上、山地80mm以上 |
|
|
24時間雨量 盆地70mm以上、山地150mm以上 |
|
|
洪水 |
1時間雨量 盆地20mm以上、ただし総雨量50mm以上 |
|
3時間雨量 盆地40mm以上、山地80mm以上 |
|
|
24時間雨量 盆地70mm以上、山地150mm以上 |
|
|
大雪 |
24時間の降雪の深さ 盆地5cm以上、山地10cm以上 |
|
濃霧 |
視程100m以下 |
|
雷 |
落雷等により被害が予想される場合 |
|
乾燥 |
実効湿度50%以下で最小湿度25%以下(気象官署の値) |
|
なだれ |
表層なだれ:24時間の降雪の深さが30cm以上で、気象の変化が激しいとき |
|
着雪(氷) |
着雪(氷)が著しく、通信線や送電線等に被害が起こると予想される場合 |
|
霜 |
早霜・晩霜期に最低気温が3℃以下 |
|
低温 |
夏期 甲府の最低気温が16℃以下の日が2日以上続く場合、 |
警報
大雨、大雪などにより重大な災害が起こる恐れがある場合、その旨を警告し発表されます。
|
種類 |
発表基準 |
|---|---|
|
暴風 |
平均風速20m/s以上 |
|
暴風雪 |
平均風速20m/s以上、雪を伴う場合 |
|
大雨 |
1時間雨量 盆地40mm以上、ただし総雨量100mm以上 |
|
3時間雨量 盆地80mm以上、山地120mm以上 |
|
|
24時間雨量 盆地150mm以上、山地250mm以上 |
|
|
洪水 |
1時間雨量 盆地40mm以上、ただし総雨量100mm以上 |
|
3時間雨量 盆地80mm以上、山地120mm以上 |
|
|
24時間雨量 盆地150mm以上、山地250mm以上 |
|
|
大雪 |
24時間の降雪の深さ 盆地20cm以上、山地40cm以上 |
8.土砂災害について
私たちが住むこの国は、国土の75%が丘陵地を含む山地であり、気候はアジアモンスーン地帯に位置していることから雨が多く、土砂災害の起きやすいところだと言えます。事実、日本全国で発生している土砂災害の件数は、毎年平均900件以上とその他の災害に比して群を抜いています。
ちなみに、国土交通省で公表している土砂災害危険箇所は、全国で525,307箇所となっており、山梨県だけでも4,805箇所にのぼります。
当市の災害履歴でも大きな災害の多くは土石流やがけ崩れによるものでした。そして、これを防ぐため現在でも山梨県では多くの砂防施設や治山施設を施工しています。
ですが、前述のとおりその箇所が非常に多くかつ県内に広く点在しているため、その全部に対して行うことは非常に厳しい状況です。また、施工済みのところであっても自然の猛威を全て防ぎきることは難しいと考えます。
特に昨今では、台風以外でも2004年7月の新潟福井豪雨で見られるように突然の集中豪雨が襲ってくることもあります。ぜひ、防災気象情報の活用や以下のことを参考にして頂き、大切な人(自分を含めた)の命を守りましょう。
※砂防指定地とは
土砂災害を防ぐため、一定の行為を制限したり砂防施設を整備する必要がある場所を砂防法2条に基づき指定しているところを言います。
この場所において以下の行為をする場合、山梨県知事の許可が必要になります。
- 施設又は工作物の新築、改築又は除去
- 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
- 竹木(枯損竹木を含む。)の伐採又は抜根
- 土砂若しくは砂れきの採取、鉱物の採取又はこれらのたい積若しくは投棄
- 竹木、土石等の滑下又は地引きによるこれらの運搬
- 家畜の放牧又は係留
- 火入れ
- その他、知事が治水上砂防のため支障があると認める行為
市内土石流危険渓流一覧
※詳細な場所については、当課若しくは山梨県都留建設部までお尋ね下さい。
9.住宅の耐震化について
平成7年1月の阪神淡路大震災では、10万棟以上が全半壊となりました。そして、犠牲となった6,400名以上の人たちのうち8割の方が、住宅の倒壊や家具の転倒による圧迫死や窒息死と言われています。また、これらによる負傷者も43,792人と戦後最悪の人的被害が出てしまいました。
そして、まだ記憶に新しい平成16年の新潟県中越地震でも16,947棟(一部損壊を加えると120,550棟)が全半壊しています。豪雪地帯特有の堅固な家が多いと言われるところでも、当市の全住宅棟数に迫るほどの住宅が被害を出しました。
地震による被害で最も恐ろしいのが、住家の倒壊による人的経済的被害です。そのため、国では大地震が発生し、住家被害が出るたびに被害の発生原因などを調査し、安全な建物構造のあり方を検討し「建築基準法」における「耐震基準」を見直し続けています。そして、現在使われている耐震基準は、1981年(昭和56年)に定められたものです。実際、阪神淡路大震災でもこの新耐震基準による建物は被害が少なかったと報告されています。
この新耐震基準以前(昭和56年5月以前)に建てられた家屋にお住まいの方は、ぜひ住宅の耐震化についてご検討ください。当市においても、住宅の無料耐震診断や耐震改修に対する補助制度を実施しておりますので、建築住宅課(内線293)までお問い合わせください。
住宅の耐震診断制度
要件
次のすべての条件をみたす住宅
- 市内に住所を有する者が所有しかつ主に居住している住宅で延べ床面積が300平方メートル以下のもの。
※複数の住宅を所有している者については、主に居住している1棟のみ対象。 - 木造在来工法で建てられた2階建以下(2階建を含みます)の戸建住宅。
※プレハブ工法、2×4工法などは対象外。 - 昭和56年5月31日以前に着工し建てられた住宅
※昭和56年6月1日以降増築工事があった場合でも可。
耐震診断費用
無料(費用は国、県、市が負担します。)
調査・診断概要
本市が委託した業者が訪問し、目視調査を原則として実施します。
また、建築設計図書などがある場合には、提示していただきます。
診断方法は、「山梨県木造住宅耐震診断マニュアル」による簡易診断です。
募集期間
本制度は、随時では無く期間を定めて希望者を募集しています。募集方法は、広報誌に掲載する形で行われますのでお気をつけ下さい。
耐震改修工事に対する補助制度
要件
- 昭和56年5月31日以前に着工した、2階建て以下の木造在来工法で建築された住宅で、「山梨県木造住宅耐震診断マニュアル」に基づく耐震診断等を受け、総合評点が1.0未満と判定された個人住宅(自己用)。
- 耐震補強計画の策定
※計画策定は建築士が行います(有料)。なお、計画策定にかかる費用は耐震工事が完了した場合には、補助対象となります(補強計画策定のみでは補助対象外。)。
対象工事
住宅の耐震性が別に定める基準値以上となるように行う耐震改修工事。
※耐震補強に結びつかない工事は除く。
補助金額
概ね耐震改修工事に要する費用の2月3日以内かつ80万円が上限となります。
|
市町村 |
水系名 |
河川名 |
渓流名 |
字 |
渓流長 |
地形分類 |
砂防指定地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-001 |
相模川 |
大沢川 |
東沢 |
小明見 |
0.12 |
扇状地形 |
2条指定 |
|
1-002 |
相模川 |
大沢川 |
向沢 |
小明見 |
0.44 |
扇状地形 |
無 |
|
1-003 |
相模川 |
大沢川 |
大沢川 |
小明見 |
2.60 |
谷底平野 |
2条指定 |
|
1-004 |
相模川 |
大沢川 |
明見沢 |
小明見 |
0.71 |
扇状地形 |
無 |
|
1-005 |
相模川 |
大沢川 |
吉原沢 |
小明見 |
0.15 |
谷底平野 |
無 |
|
1-006 |
相模川 |
桂川 |
古屋川 |
大明見 |
2.70 |
谷底平野 |
2条指定 |
|
1-007 |
相模川 |
桂川 |
かんな堀沢 |
大明見 |
0.76 |
扇状地形 |
無 |
|
1-008 |
相模川 |
桂川 |
平山沢 |
大明見 |
0.62 |
扇状地形 |
無 |
|
1-009 |
相模川 |
桂川 |
間堀川 |
上吉田 |
9.70 |
扇状地形 |
無 |
|
1-010 |
相模川 |
桂川 |
浅間沢 |
上吉田 |
5.07 |
扇状地形 |
無 |
|
1-011 |
相模川 |
桂川 |
神田堀川 |
上吉田 |
8.77 |
扇状地形 |
無 |
|
1-012 |
相模川 |
桂川 |
宮川 |
松山 |
10.70 |
扇状地形 |
2条指定 |
|
1-013 |
相模川 |
桂川 |
嘯沢 |
新倉 |
0.15 |
谷底平野 |
無 |
|
1-014 |
相模川 |
宮川 |
旭沢の2 |
旭町 |
0.47 |
谷底平野 |
無 |
|
1-015 |
相模川 |
宮川 |
旭沢の1 |
旭町 |
0.73 |
谷底平野 |
無 |
|
1-016 |
相模川 |
宮川 |
入山川 |
富士見町 |
1.07 |
谷底平野 |
2条指定 |
|
1-017 |
相模川 |
桂川 |
入山沢の1 |
浅間町 |
0.16 |
谷底平野 |
無 |
|
1-018 |
相模川 |
宮川 |
石屋ヶ沢の2 |
宮下町 |
0.08 |
谷底平野 |
無 |
|
1-019 |
相模川 |
桂川 |
大石沢の1 |
富士見町 |
0.23 |
谷底平野 |
2条指定 |
|
1-020 |
相模川 |
桂川 |
大石沢の2 |
富士見町 |
0.12 |
谷底平野 |
無 |
|
1-021 |
相模川 |
桂川 |
要沢 |
富士見町 |
0.53 |
谷底平野 |
2条指定 |
|
1-022 |
相模川 |
桂川 |
西沢 |
富士見町 |
0.12 |
谷底平野 |
2条指定 |
|
1-023 |
相模川 |
桂川 |
数見川 |
寿町 |
1.72 |
谷底平野 |
2条指定 |
|
1-024 |
相模川 |
桂川 |
金山沢 |
白糸町 |
1.70 |
谷底平野 |
2条指定 |
|
1-025 |
相模川 |
桂川 |
海久保沢 |
白糸町 |
0.24 |
谷底平野 |
無 |
|
1-026 |
相模川 |
桂川 |
殿入沢 |
白糸町 |
0.12 |
谷底平野 |
無 |
|
1-027 |
相模川 |
桂川 |
殿入川 |
白糸町 |
1.37 |
谷底平野 |
2条指定 |
|
1-028 |
相模川 |
桂川 |
白糸沢 |
白糸町 |
0.28 |
谷底平野 |
無 |
|
2-001 |
相模川 |
桂川 |
不動沢 |
富士見町 |
0.34 |
谷底平野 |
2条指定 |