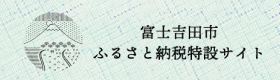本文
健康コラム第13弾 メタボ予防におすすめ(食事の摂り方編)
メタボリックシンドロームの方の食事改善においては、食事内容の見直しだけではなく、食事の摂り方も意識しましょう
1日3食、規則正しく食べましょう
摂取カロリーをコントロールするために、昼食や夕食を抜く方がいらっしゃいますが、欠食をすることで食事の間隔があいてしまうと、体が飢餓状態となり、エネルギーを貯めこみやすくなってしまいます。そしてさらに間食しやすくなり、食べ過ぎてしまう可能性もあります。
毎日同じ時間帯に、1日3食規則正しく食事をとりましょう。
食物繊維が豊富な食品から食べましょう
食物繊維は糖質や脂質を吸収して体外に排出する作用があり、消化に時間がかかる食物繊維から食べ始めることで、糖質や脂質の吸収が穏やかになります。また、食物繊維は満足感を得ることもでき、食べ過ぎ回避にも繋がります。
まずは、食物繊維が豊富な「野菜」「海藻類」「きのこ類」から食べましょう。
よく噛んでゆっくり食べましょう
食事をよく噛んで味わって食べることで満腹感が得やすくなり、少しの食事量でも満足感が得られます。満腹中枢が刺激されるのは、食事を始めてから20分後と言われています。
一食あたり20分以上の時間をかけ、食事をゆっくりと味わうよう意識しましょう。
腹八分目でお箸を置きましょう
「もう少し食べたいな…」と思ったタイミングでお箸を置く癖が付けば、食べ過ぎを回避することができます。
腹八分目で食べ終えるのが難しい方は、食事前や食事中にこまめに水分をとる、小皿に取り分けておくなどの対策がおすすめです。
間食やデザートはなるべく控えましょう
カロリーが高いお菓子、糖質や脂質が高いおやつなどを、間食やデザートとして食べるのは控えましょう。
「絶対に間食やデザートを食べてはダメ」という訳ではありません。身体が飢餓状態になってしまうと、エネルギーを貯めこみやすくなり、食事を食べ過ぎてしまいます。摂取カロリー・脂質量・糖質量に気を付けて、食べ過ぎないよう注意をすれば間食やデザートを食べることはできます。
夕食は21時までに食べ終えるようにしましょう
人間のDNAに結合している「BMAL1(タンパク質)」には、脂肪細胞を作るために必要な酵素を増やす働きがあります。このBMAL1は午後10時~午前2時の分泌量が、昼の20倍になるため、21時以降に夕食や夜食を摂取すると脂肪細胞が増えやすくなってしまいます。
どうしても21時以降しか食事を取れない方は、炭水化物を夕方に食べておき、21時以降はおかずのみを食べる「分食」されると良いでしょう。
お酒の飲み過ぎに気をつけましょう
種類を問わずアルコールは高カロリーな上に、ステロイドというホルモン分泌を促して内蔵脂肪がつきやすくなります。さらにお酒のつまみは脂質や糖質が高いものが多く、摂取エネルギー自体が増えてしまうこともデメリットです。1日のアルコールの適量は、ビールであれば500ml、ワインであれば2杯程度にしておき、週2回はお酒を飲まない日「休肝日」を設けられると良いでしょう。
しっかり休肝日を設け、飲み過ぎないようにしましょう。
最後に大切なのは「継続」することです
メタボリックシンドロームと診断された人や、予備軍であると言われた人は、年齢・性別・運動量に合った食事内容や食習慣を改善することが一番の対策です。しかし、無理をして過度な食事制限をしてしまうと、すぐにリバウンドしてしまいます。
メタボリックシンドロームの予防や対策であれば、無理のない範囲で食事内容を見直し、長期的に継続することが大切です。