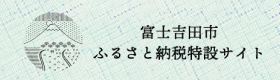本文
地下水の水質測定調査 用語の解説
| 検査項目 | 基準値 | 項目説明 |
|---|---|---|
| 一般細菌 | 100個/mL以下 | 消毒効果の確認や一般的清浄度を示す指標となります。河川水では、降雨によっても値が高くなりますが、地下水での上昇は微生物汚染が生じた可能性を示します。平常時は水道水中には極めて少ないのですが、著しく増加した場合には生物的汚染が生じている疑いを示します。 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 水系感染症の主な原因菌が人を含む温血動物の糞便によるものであることから、飲料水の微生物学的安全性を確保するためには、糞便汚染を検知することが極めて重要です。この糞便汚染を確認するための指標として、大腸菌による汚染の有無を確認することが適当とされています。 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 | 硝酸塩は、窒素化合物が土壌や水中の細菌によって分解されて生じた最終生成物で、亜硝酸塩は分解過程の途中の生成物です。窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水などの混入によって河川水等で検出されます。高濃度に含まれると幼児にメトヘモグロビン血症(チアノーゼ症)を起こすことがあります。 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 地質由来の場合もありますが、鉱山排水、工場排水などの混入や、鉄管に由来して検出されることがあります。高濃度に含まれると異臭味(カナ気)や、洗濯物を着色する原因となります。給水管の腐食によるものが多いようです。0.3mg/L以上では赤水の原因となり、0.5mg/L以上では鉄臭さや苦味を感じます。 |
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 地質や海水の浸透など天然に由来するものが多いですが、下水、家庭排水、工場排水及びし尿などから河川への混入により増加することがあります。高濃度に含まれると味覚を損なう原因となります。 |
| 硬度 (カルシウム、マグネシウム等) |
300mg/L以下 | 硬度とは、カルシウムとマグネシウムの塩類の合計量をいいます。主として地質によるものですが、工場排水、下水などの河川への混入により増加します。硬度が低すぎると淡泊でコクのない味がし、硬度が高すぎると硬くてしつこい味がします。WHO飲料水水質ガイドラインでは0~120mg/Lまでを軟水、それ以上を硬水といいます。硬度の高い水は、湯沸かし器などへのスケールの付着を起こしたり、石けんの泡立ちを悪くします。 |
| 有機物等 (全有機炭素(TOC)の量) |
3mg/L以下 | 有機物は土壌に起因するほか、し尿、下水、工場排水などの混入によって増加します。全有機炭素は有機化合物を構成する炭素の量を示すもので、TOC計を用いることによってさらに精度の高い測定を行うことができます。有機物汚染の指標に用いられます。 |
| pH値 | 5.8~8.6 | 酸性、アルカリ性の指標で、pH7が中性です。7より小さくなるほど酸性が強く、7より大きくなるほどアルカリ性が強くなります。降雨、地層の影響、土壌、工業排水、汚濁物質の混入により、河川水のpHが変化します。 |
| 味 | 異常でないこと | 不純物の混入や、微生物発生の指標です。水の味は、地質などに由来します。海水、工場排水、化学薬品、農薬等の河川への混入及び藻類等生物の繁殖により、異臭味を感じることがあります。 |
| 臭気 | 異常でないこと | 不純物の混入や微生物発生の指標です。藻類等の繁殖、工場排水、下水、農薬などの河川への混入により、異臭を感じることがあります。 |
| 色度 | 5度以下 | 水についている色の程度を示すものです。基準値の範囲内であれば無色な水といえます。フミン質(落ち葉などが腐った後の残骸で、トリハロメタンなどの原因)の黄色、鉄による赤、マンガンによる黒、銅による青などの着色があります。 |
| 濁度 | 2度以下 | 水の濁りの程度を示すものです。基準値の範囲内であれば濁りのない透明な水といえます。水道水は濁度が0.1度未満になるように浄水処理を行っています。 |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 揮発性有機塩素化合物の1種で、無色透明の液体です。主な用途としては、金属機械部品等の脱油洗浄、ドライクリーニング、香料等の抽出、染料の溶剤等があります。人体への影響としては、肝障害、腎障害、中枢神経障害が知られています。また、廃液等による地下水汚染の進行が懸念されています。 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 揮発性有機塩素系化合物の1種で、無色透明の液体です。主な用途としては、ドライクリーニング、溶剤等があります。人体への影響としては、肝障害、腎障害、中枢神経障害が知られています。また、廃液等による地下水汚染の進行が懸念されています。 |
| 1.1.1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 | 有機塩素化合物の1種で、甘い臭いを持つ無色透明の液体です。主な用途としては、金属洗浄剤、ドライクリーニング用溶剤等があります。人体への影響としては中枢神経障害が知られています。廃液等による地下水汚染が懸念されています。また、四塩化炭素と同様に、オゾン破壊物質としてモントリオール議定書にリストアップされています。 |
| カドミウム | 0.003mg/L以下 | 青白色の光沢を持つ柔らかい金属です。地殻中の存在量は約0.02mg/kgとわずかですが、亜鉛と共存する形で自然界に広く分布しており、特に汚染を受けていない地表水や地下水中にも、亜鉛の1/100から1/150程度の量(約0.1~0.5μg/リットル)が含まれているといわれています。主な用途としては、顔料、プラスチック、電池、金属加工等があります。人体に対する毒性は強く、急性毒性では数グラムの摂取で激しい胃腸炎を起こして死亡した例もあります。公害病として有名なイタイイタイ病は、慢性中毒による腎機能障害、カルシウム代謝異常に、妊娠、授乳、栄養素としてのカルシウム不足などの要因が重なって発症した重症の骨軟化症とされています。 |
| 全シアン | 検出されないこと | シアンは、自然水中にはほとんど含まれませんが、メッキ工場や金属精錬所など青酸化合物を使用する事業所などの排水の混入によって含まれることがあります。青酸カリに代表されるように、シアン化合物は一般に毒性が強く、微量でも水生生物や下水浄化微生物に障害を与えます。 |
| 鉛 | 0.01mg/L以下 | 蒼白色のやわらかく重い金属で、地殻中の存在量は約13mg/kgです。古くから人類に利用されてきた金属の1つで、現在でもそのさびにくさ、加工しやすさを利用して鉛管、板、蓄電池等、金属のまま使用されるほか、その化合物も広く利用されています。人体への影響としては貧血や、中枢神経等への影響があります。 |
| 六価クロム | 0.05mg/L以下 | 銀白色の硬くて脆い金属で、地殻中の存在量は、約100mg/リットルです。水中のクロムは通常3価と6価の形で存在します。このうち6価クロムは主にクロム酸(CrO42-)や重クロム酸(Cr2O72-)の形をとり、特にpHが酸性のときは酸化力が強く、有毒です。主な用途としては、顔料、電気メッキ等があり、これらの廃液や、クロム鉱さいからの浸出水による地下水汚染が報告されています。人体への影響としては、皮膚潰瘍、鼻中隔穿孔、肺がん等があります。 |
| ヒ素 | 0.01mg/L以下 | 地殻中の存在量は1.8mg/kgで多くは硫化物として産出します。海水中には2μg/リットル程度含まれていますが、一般河川にはあまり含まれていません。しかし、温泉水など火山地帯の地下水には数十mg/リットルの高濃度で含まれていることがあります。砒素は昔から毒薬として知られてきましたが、現在では半導体の原料、医薬品、農薬、防腐剤など広く利用されています。人体への影響としては、皮膚の色素沈着、下痢や便秘等があります。砒素中毒による事故としては、乳分の安定剤への砒素混入が原因とされる森永砒素ミルク事件(昭和30年)があります。また、鉱山操業時の環境汚染が原因とされる慢性砒素中毒が宮崎県土呂久鉱山及び島根県笹ヶ谷鉱山の周辺地区で発生しています。 |
| 総水銀 | 0.0005mg/L以下 | 無機水銀と次項で述べる有機水銀をあわせたものです。水銀は、銀白色で、常温では唯一の液体金属です。地殻中の存在量は約0.08mg/kgで主に赤色硫化物である辰砂(HgS)として産出します。水銀は古くから知られており、防腐、消毒等に使用されてきました。また金鉱山での金の精錬にも使用されてきました。現在でも化学品製造、医薬品、乾電池などに使用されています。水銀化合物中には昇こう(HgCl2)のように強い毒性を持つものが有ります。また慢性中毒では興奮傾向、不眠といった中枢神経への影響が見られます。 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 揮発性有機化合物の1種で、無色透明の液体で不燃性です。主な用途としては、不燃性の溶剤、ドライクリーニング用等があります。人体への影響としては、肝障害、腎障害、中枢神経障害が知られています。また、オゾン破壊物質としてモントリオール議定書(「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」)にリストアップされています。 |
| ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | 粘性のある油状物質で、天然には存在しない合成有機塩素化合物です。熱や酸・アルカリに対して強く、電気絶縁性が高いなど工業的に利用度が高く、トランス油、コンデンサー、熱媒体、ノーカーボン紙等に広く利用されていました。人体への影響としては、皮膚への色素沈着、消化器障害、肝障害などがあり、PCBは脂肪組織への蓄積系が高いため、症状は長期にわたるといわれています。また、胎盤透過性があり、乳汁中にも排泄されるため、胎児や乳児にも障害が及ぶとされています。昭和43年に西日本を中心として発生したカネミ油症事件は、米ぬか油の製造過程でPCBが混入したことが原因とされています。 |
| 電気伝導率 | - | 水による電気の伝え易さを示す指標です。真の純水は電気を伝えないので、電気伝導率は0ですが、水に雑物が溶け込んでくると電気を伝え易くなります。したがって、電気伝導率は、水に溶け込んでいる雑物(汚れ)の多少を示す指標です。清浄な河川で100μS/cm内外です。 |