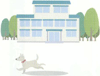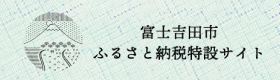本文
介護予防サービスの利用の流れ(要支援1・2の方)
介護認定で要支援1・2と判定された方への介護予防サービスです。
介護予防サービスは、要支援1、2と認定された方が、今よりも状態が悪くならないように、また少しでも自分でできることが増えるようになるために、利用していただくサービスです。
(1)連絡・契約
- 要支援1・要支援2と認定された結果通知が届いたら、地域包括支援センター(市役所東庁舎1階健康長寿課内)に連絡、相談をします。
- 地域包括支援センターでは職員が重要事項について説明するので、同意したら契約を結びます。
【Aさん 75歳 要支援2】
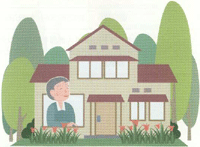
 地域包括支援センターでは専門性の高い職員が対応します。
地域包括支援センターでは専門性の高い職員が対応します。
※ケアマネージメント等につきまして地域包括支援センターから事業所へ委託する場合がございます。

(2)話し合い(課題分析)
家族や地域包括支援センターの職員と今どのようなことで困っているのか、これからどのような生活を希望するのかなどについて話し合います。
「腰が痛いので家事をヘルパーさんに手伝ってほしい」
「でも、身の回りのことは自分でできるようになりたい」
「無理をしないでもできる運動はないかな?」
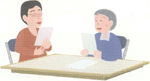

地域包括支援センターの職員は、話し合いを通じて利用者や家族が抱える問題を見つけ出します。そして、その問題の解決方法をいっしょに考えます。

(3)介護予防ケアプランの作成
地域包括支援センターの職員といっしょに、具体的な目標や利用する介護予防サービスなどを定めた介護予防ケアプランを作ります。
◇目標◇できる範囲で自分の部屋のそうじを行う。

介護予防通所リハビリテーションを利用することにしました。


地域包括支援センターの職員が、利用者にあった目標や介護予防サービスなどを提案してくれます。

(4)サービスの利用開始
- 介護予防サービス事業者と契約します。
- 介護予防ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
- 利用したサービス費用の1~3割を支払います。
※所得の状況などにより、負担割合は変わります。


利用者がサービスを利用し始めた後も、地域包括支援センターでは利用者の状態を見守り続けています。

(5)評価・見直し
- 地域包括支援センターは、一定期間後に介護予防ケアプランで設定された目標が達成されたかどうかを評価します。
- 評価の結果、介護予防ケアプランの見直しが必要とされた場合は、より利用者にあった介護予防ケアプランに作り直します。