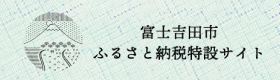本文
帯状疱疹予防接種
令和7年4月から、帯状疱疹予ワクチン接種を予防接種法に基づく定期の予防接種に追加する方針が決定しました。
これにより、対象の年度年齢の方への定期接種が開始されます。
- 満50歳以上を対象とした任意接種の助成制度は令和7年9月30日で終了します。
- 過去に帯状疱疹ワクチンの予防接種を受けた方は、基本的には助成対象外となります。
- この予防接種は強制ではありません。本人が希望する場合に限り接種を行います。
- 接種時の年齢等により「定期接種」「任意接種」に区分されますが、定期接種・任意接種にかかわらず助成は生涯1度のみです。次の早見表を参考のうえ、接種のタイミングを決めてください。
令和7年度 帯状疱疹早見表 [PDFファイル/807KB](早見表)
帯状疱疹とは
水痘帯状疱疹ウイルスに初めて感染すると水痘(水ぼうそう)を発症し、治った後もウイルスが神経に潜伏します。その後加齢や免疫低下によりウイルスが再活性化することによって帯状疱疹を発症し、80歳までに約3人に1人が発症するといわれています。
症状の特徴として、皮膚に分布している神経に沿って、水ぶくれを伴う赤い発疹が身体の片側に帯状に現れます。通常、発疹の出現2日から3日前にかゆみ、もしくはピリピリとした痛みが現れ、初期は皮膚が赤く腫れます。1週間程度経過すると、水ぶくれが増え、発熱、頭痛、リンパ節の腫れなどの症状も現れます。通常は2週間から4週間で水ぶくれが破れて痂皮化(かさぶたになる)し、皮膚症状がおさまります。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛(Phn)」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
帯状疱疹のワクチン
帯状疱疹ワクチンは2種類あります。接種回数やスケジュール、接種条件、効果の持続期間、副反応などの特徴が異なっていますので、下記の表などを参考に医師等とご相談の上、2種類ワクチンのうちいずれかを選択してください。
※生ワクチン、不活化ワクチン両方の助成を受けることはできません。
| 種類 | 生ワクチン | 不活化ワクチン |
|---|---|---|
|
名称 |
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」 |
| 助成額 | 1回あたり4,400円 | 1回あたり11,000円 |
| 接種回数 | 1回 | 2回 |
| 効能 | 水ぼうそう・帯状疱疹の予防 | 帯状疱疹の予防 |
| 帯状疱疹に対する予防効果 |
1年後:6割程度 |
1年後:9割以上 |
| 帯状疱疹後 神経痛に対する予防効果 |
3年後:6割程度 | 3年後:9割以上 |
| 接種方法 | 皮下注射 | 筋肉内注射 |
|
主な副反応 |
接種部位の発赤・そう痒感・熱感・腫脹・疼痛、関節痛、倦怠感等 |
接種部位の疼痛・発赤・腫脹、倦怠感、頭痛、筋肉痛、悪寒等 |
| 注意事項 |
・明らかに免疫機能に異常のある疾患をお持ちの方及び免疫機能の低下をきたす治療を受けている方は接種できません。 |
・通常2か月以上の間隔をあけて6か月までに2回目を接種します。 |
※ 不活化ワクチンの場合、通常2か月以上の間隔をあけて6か月までに2回目を接種します。
(ただし、病気や治療により、免疫の機能が低下した又は低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。)
定期接種
定期接種の対象者(令和7年度)
定期接種の対象者には、予診票(緑色)が送付されます。(4月上旬)
- 令和7年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
- 100歳以上の方(令和7年度のみ)
- 60歳から64歳の方のうち、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する市民の方(身体障がい者1級相当)
令和7年度から令和11年度の5年間は、経過措置のため対象者は5歳刻みとなり、令和12年度以降は、接種日時点で65歳の方のみが対象になります。
※過去に帯状疱疹ワクチンの予防接種を受けた方は、基本的には助成対象外となります。
(過去に組換えワクチンを1回受けた方は、残りの1回分のみ助成の対象となります)
※接種日時点で富士吉田市に住民登録のある方に限ります。
| 65歳 | 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 | 70歳 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 |
| 75歳 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 80歳 | 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 |
| 85歳 | 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 90歳 | 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 |
| 95歳 | 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 | 100歳以上 | 大正15年4月1日以前に生まれた方 |
定期接種の実施期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日) の間
※実施期間外での接種は全額自己負担になります。
※不活化ワクチンを接種する場合、遅くともR8年1月31日までに1回目の接種をしてください!
定期接種の助成額
| ワクチンの種類 | 接種回数 | 助成額 |
|---|---|---|
| 生ワクチン | 1回 | 4,400円 |
| 不活化ワクチン | 2回 | 1回あたり11,000円ずつ |
助成額を超える金額は自己負担となります。直接医療機関へお支払いください。
接種にかかる費用・使用するワクチンは医療機関によって異なります。
定期接種を受ける流れ
-
予診票(緑色)を手元に用意する。
定期接種対象者には予診票が発送されます。(4月上旬)
お手元に届いた予診票を紛失等した場合、本人確認書類を持参の上、健康長寿課で再発行手続きをしてください。 - 帯状疱疹予防接種指定医療機関一覧を見て、接種したい医療機関を決める。
帯状疱疹医療機関一覧はこちら→帯状疱疹 医療機関一覧 [PDFファイル/451KB] - 医療機関に予約を取る。
※指定医療機関で接種のご予約を行う際、接種を希望するワクチン(生ワクチン/不活化ワクチン)をお伝えください。
※指定医療機関によってワクチンの在庫状況等が異なりますので、ご予約の際に接種できるワクチンについてご確認ください。
※指定医療機関によって接種費用が異なりますので、ご予約の際に費用についてご確認ください。 - 予約日に医療機関へ行き、予防接種を受ける。
※お手元に届いた予診票をお持ちください(定期接種の場合、対象者に市から郵送されます)。
※ワクチン接種の効果や副反応、予防接種健康被害救済制度についてご理解の上、予診票を正しく記入し、医師からの説明を受けましょう。
※医療機関窓口では、接種費用から市の助成金額を差し引いた額を自己負担額としてお支払いください。
定期接種の接種場所
医療機関へ直接ご予約ください!
医療機関一覧はこちら→帯状疱疹 医療機関一覧 [PDFファイル/451KB]
※指定医療機関一覧は、随時更新します。
(使用するワクチンについては、医療機関にご確認ください。)
やむを得ない場合の指定医療機関以外での接種方法はこちら
定期接種の持ち物
■送付された予診票(緑色)
※予診票のない方は接種できません。必ずお持ちください。
■本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
■接種料金(自己負担分)
予防接種健康被害救済制度(定期接種)
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
予防接種を受けたことによる健康被害が起きた場合の詳細はこちら→予防接種健康被害救済制度について(厚労省HP)<外部リンク>
任意接種
令和7年4月から、帯状疱疹ワクチン接種が定期接種になったことに伴い、市独自の帯状疱疹任意接種への助成は令和7年9月30日で終了します。
任意接種の助成対象者
接種日時点で、満50歳以上の方
※接種日時点で富士吉田市に住民登録のある方に限ります。
※50歳を迎える方の不活化ワクチンでの接種の場合、助成対象の時期に注意してください。
(例えば昭和50年8月1日生まれの方が1回目を令和7年8月1日に、2回目を令和7年10月1日に接種する場合、2回目の接種は助成の対象に含めることはできず、全額自己負担となります。)
任意接種の助成実施期間
令和7年9月30日(火曜日) まで
※実施期間外での接種は全額自己負担になります。
※不活化ワクチンを接種する場合、遅くとも令和7年7月30日までに1回目の接種をしてください!
任意接種の助成額(令和7年度)
| ワクチンの種類 | 接種回数 | 助成額 |
|---|---|---|
| 生ワクチン | 1回 | 4,400円 |
| 不活化ワクチン | 2回 | 1回あたり11,000円ずつ |
助成額を超える金額は自己負担となります。直接医療機関へお支払いください。
接種にかかる費用・使用するワクチンは医療機関によって異なります。
任意接種を受ける流れ
- 自分が対象者かどうか確認する。
- 帯状疱疹予防接種指定医療機関一覧を見て、接種したい医療機関を決める。
こちら→帯状疱疹 医療機関一覧 [PDFファイル/451KB] - 医療機関に予約を取る。
※指定医療機関で接種のご予約を行う際、接種を希望するワクチン(生ワクチン/不活化ワクチン)をお伝えください。
※指定医療機関によってワクチンの在庫状況等が異なりますので、ご予約の際に接種できるワクチンについてご確認ください。
※指定医療機関によって接種費用が異なりますので、ご予約の際に費用についてご確認ください。 - 予約日に医療機関へ行き、予防接種を受ける。
※予診票は各医療機関でお受け取りください(任意接種の場合、市から予診票の交付はありません)。
※医師から、ワクチン接種の効果、副反応、医薬品副作用被害救済制度について説明を受けましょう。
※医療機関窓口では、接種費用から市の助成金額を差し引いた額を自己負担額としてお支払いください。
任意接種の接種場所
医療機関へ直接ご予約ください!
医療機関一覧はこちら→帯状疱疹 医療機関一覧 [PDFファイル/451KB]
※指定医療機関一覧は、随時更新します。
(使用するワクチンについては、医療機関にご確認ください。)
任意接種の持ち物
■本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
■接種料金(自己負担分)
予防接種健康被害救済制度(任意接種)
万が一、接種後生じた健康被害は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済給付の対象、富士吉田市予防接種事故災害補償規則に基づく補償の対象となる場合があります。
予防接種を受けたことによる健康被害が起きた場合はこちら→独立行政法人 医薬品医療機器総合機構HP<外部リンク>