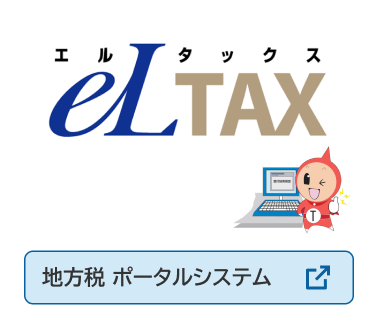本文
国民健康保険税 概要
国民健康保険財源は、加入者の皆さまに納めていただく国民健康保険税を主な財源として、それに加えて国や都からの負担金・補助金、市一般会計からの繰入金(国保への財源補てん)などを財源として、運営しています。
1.国民健康保険税について
納税義務者(世帯主課税)
国民健康保険税は、世帯主に課税されます。
世帯主が国民健康保険の被保険者でなくても、世帯に国民健康保険の被保険者がいると、世帯主が納税義務を負うこととされています(擬制世帯主)。ただし、被保険者でない世帯主の所得は課税の対象とはなりません。
税額の計算
国民健康保険税は、「医療分」と「支援金分」と「介護分」の合算額です。
「医療分」と「支援金分」は年齢に関係なく国民健康保険の被保険者全員に算定され、「介護分」は40歳以上65歳未満の被保険者についてのみ算定されます。
上記の3つの分類それぞれで、該当者ごとに「所得割」・「均等割」を算定し、世帯全員分の合計に「平等割」を加えたものが世帯の年間の税額となります。
令和4年度より子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児に係る均等割を2分の1減額します。
税率
| 区分 | 課税の基礎 | 税率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 支援金分 | 介護分 | ||
| 所得割 | 総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額 | 7.70% | 2.50% | 1.90% |
| 均等割 | 被保険者1人について | 25,200円 | 8,400円 | 10,200円 |
| 平等割 | 被保険者のいる1世帯について | 21,600円 | 6,600円 | 6,000円 |
| 課税限度額 | 66万円 | 26万円 | 17万円 | |
株式等の譲渡所得および配当等の所得について
所得税、個人市・県民税(住民税)が源泉されている「源泉徴収あり」を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得、上場株式等の特定配当等の所得を申告した場合は、保険税を算定する上での総所得金額等に含まれます。
この所得を申告された場合、所得税や個人市・県民税で損益通算したり税額控除を受けることができますが、申告した結果、保険税が増額となる場合があります。
国民健康保険に加入している方は、この所得を申告することによる個人市・県民税や国民健康保険税への影響を総合的によく考慮した上で、申告するかしないかをご自身で判断する必要があります。
月割課税
年の途中で国保資格の取得・喪失、転入・転出などがあった場合は、月割(加入した月分)で国民健康保険税を計算します。
国保資格の取得・喪失は、届出日ではなく実際の取得・喪失日です。
- 国保に加入する場合・・・・・・加入した月から月割で算定します。
- 国保を脱退する場合・・・・・・脱退した月の前月まで月割で算定します。
なお特定の年齢(40・65・75歳)に到達した際、税額が変更されますのでご注意ください。
| 年齢 | 国保税 | 介護保険料 | 後期高齢者医療保険料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 支援金分 | 介護分 | |||
| ~39歳 | ○ | ○ | |||
| 40歳~64歳 | ○ | ○ | ○ | ||
| 65歳~74歳 | ○ | ○ | ○ | ||
| 75歳~ | ○ | ○ | |||
年度の途中で40歳になられる方は、新しく介護分が賦課されます。40歳に達した年度の介護納付金については誕生月から月割で算定し、誕生月の翌月以降に通知をお送りします。
例 9月誕生日(40歳到達) ↠ 介護分:7か月間(9月~翌3月) ※10月以降に送付
年度の途中で65歳になられる方は、介護分の賦課が停止になります。65歳に達した年度の介護納付金については誕生月の前月分までを月割で算定します。なお誕生月の翌月以降に介護保険料の通知を別途お送りします。
例 9月誕生日(65歳到達) ↠ 介護分:5か月間(4月~8月)
介護保険料:7か月間(9月~翌3月) ※10月以降に送付
年度の途中で75歳(一定障害のある方は65歳)になられる方は、後期高齢者医療制度に移行します。75歳に達した年度の国保税については誕生月の前月分までを月割で算定します。なお誕生月の翌月以降に後期高齢者医療保険料の通知を別途お送りします。
例 9月誕生日(75歳到達) ↠ 国民健康保険税:5か月間(4月~8月)
後期高齢者医療保険料:7か月間(9月~翌3月) ※10月以降に送付
2.国民健康保険税の軽減・減免措置について
低所得世帯に対する軽減
前年の所得が一定以下の世帯は、下記のとおり 均等割額、平等割額を軽減します。
※軽減の申請は必要ありませんが、所得未申告の世帯は軽減が適用されませんので、必ず申告をしてください。
| 軽減割合 | 基準となる所得金額 (擬制世帯主を含む世帯主と被保険者全員前年中所得の合計額) |
|---|---|
| 7割軽減 | 世帯の所得の合計額が 43万円 +{(給与所得者等の人数 - 1)× 10万円} 以下 |
| 5割軽減 | 世帯の所得の合計額が 43万円 +{(給与所得者等の人数 - 1)× 10万円}+被保険者数 × 30.5万円 以下 |
| 2割軽減 | 世帯の所得の合計額が 43万円 +{(給与所得者等の人数 - 1)× 10万円}+被保険者数 × 56万円 以下 |
※{(給与所得者等の人数 - 1)}の部分については、世帯内の給与所得者の数が2以上の場合のみ適用となります。
※給与所得者等の人数とは、納税義務者並びに世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与所得を 有する者(給与収入が55万円を超える者)及び公的年金等に係る所得を有する者(65歳未満の場合、公的年金の収入が60万円を 超える者であり、65歳以上の場合、公的年金等の収入が110万円を超える者であり、給与所得を有する者を除く)の合計数を言います。
軽減を判定する際の所得金額について
- 土地等の譲渡所得の特別控除は認められません。
- 専従者給与は支払者の所得金額として計算されます。
- その年の1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者については、公的年金等に係る雑所得から15万円を差し引いた金額で軽減を判定します。
非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について
倒産や解雇など非自発的な理由により離職を余儀なくされた方に対し、国民健康保険税を軽減します。
※ただし軽減を受けるには申請が必要です。
詳しくは「非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について」から
後期高齢者医療制度に伴う経過措置について
保険料の軽減判定について
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することで、世帯の国民健康保険被保険者が減少しても、従前どおり後期高齢者の所得及び人数も含めて軽減判定を行います。
平等割の課税について
後期高齢者医療制度に該当した方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより国民健康保険の被保険者が1人になる世帯(特定世帯)について、5年間は平等割が半額、その後3年間は平等割が4分の1減額となります。
旧被扶養者に係る課税について
後期高齢者医療制度に該当した方が職場の健康保険(被用者保険)から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者(65歳から74歳までの方)から国民健康保険の被保険者になった方(旧被扶養者といいます)について、以下の減免措置を受けることができます。
※ただし減免の申請が必要です。
- 旧被扶養者の所得割は賦課しません。
- 資格取得から2年を経過する月の前月までの間、均等割は半額となります。また、旧被扶養者だった人のみで構成される世帯については、平等割も同様の期間に限り半額となります。(※ただし7,5割軽減世帯を除きます。)
産前産後期間の所得割・均等割軽減制度について
出産もしくは出産予定の被保険者に係る、出産(予定)日の属する月の前月(多胎は3か月前)から出産(予定)日の属する月の翌々月までの4か月(多胎は6か月)分の所得割と均等割を軽減します。
※ただし軽減を受けるには申請が必要です。
その他の減免制度について
災害、刑事施設等への拘禁等、特別の事由があると認められる場合、減免を受けられる場合があります。ただし、減免の申請が必要です。
3.納付方法について
普通徴収
納付書または口座振替による納付方法です。下記の特別徴収に該当されない場合は、普通徴収により納付していただきます。納付期間は、7月~翌年2月までの8回です。
特別徴収
特別徴収の対象者となる要件次の(1)~(4)の要件を全てに該当する場合、特別徴収の対象となります。
(1)世帯主が国民健康保険の被保険者であること
(2)世帯内の国民健康保険の被保険者全員が、年齢65歳から74歳までであること
(3)特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
(4)国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1以下の金額であること。
※お申し出により口座振替で納めていただくことができます。なお、年金からの引き落としが中止されるのは、お手続きいただいてからおよそ2か月以降の年金支払日からとなりますので、あらかじめご了承ください。
新たに該当になる方
特別徴収が開始されるまでの7月から9月(納期第1期から第3期)に納めていただく国民健康保険税は普通徴収となりますので、今までどおり納付書または口座振替により納めていただくことになります。10月からは特別徴収が開始されますので、10月、12月、2月の3回で年金月ごとに特別徴収の方法により納付していただくことになります。
前年から引き続き該当となる方
4月、6月、8月、10月、12月、2月の6回ですべて特別徴収の方法により納付していただくことになります。
※年度途中に世帯主または世帯内の国民健康保険被保険者が75歳に到達し後期高齢者医療制度に移行する場合は、特別徴収は行いません。
特別徴収から口座振替へ納付方法の変更を希望される方
- 口座振替でのお支払いを希望される方は、各金融機関および市役所税務課(市民税担当)へ届出が必要となります。
預金通帳ではなくキャッシュカードでお手続きされる方は、市役所のみでお手続きが可能です
(1)市役所税務課(市民税担当)での手続きに必要なもの(年金天引きの中止申請)
- 国民健康保険制度の被保険者証
- 印鑑
- キャッシュカード(ある方のみ)
(2)金融機関での手続きに必要なもの(口座振替の開始申請)
※キャッシュカードではなく、預金通帳で手続きをする方に限る
- 振替口座の預金通帳
- 通帳のお届印
※国民健康保険制度につきましては、下記市役所担当窓口までお問い合わせください。
4.国民健康保険税の申告について
申告の必要ない人
- 確定申告または市・県民税(住民税)の申告をした人
- 給与所得のみの人で、給与支払報告書が会社から市役所に提出されている人
- 公的年金以外に所得がない場合で、公的年金支払報告書が市役所に提出されている人
申告が必要な人
- 上記以外の人で、国民健康保険税の納税義務者(世帯主)及びその世帯に属する被保険者
※所得税や市・県民税(住民税)の申告が必要なしといわれた所得金額の人でも、国民健康保険の加入者は、申告が必要となります。
申告期限
- 毎年4月15日まで
(国民健康保険税の賦課期日(4月1日)後に納税義務が発生した場合は、発生した日から15日以内)
※所得金額が均等割額と平等割額の減額(軽減)措置に該当する方でも、申告をしないと減額(軽減)措置を受けられません。
5.納税通知書 兼 特別徴収開始(停止)通知書
税額・納付書等の通知は、毎年7月中旬頃に送付いたします。
今年転入された方へ
転入者の方につきましては、前住所地に所得照会をしております。その回答結果次第では、当初の通知書の国民健康保険税の金額が変更となり、翌月以降に再度通知書を発送させていただく場合がありますので、ご了承ください。(前住所地からの所得に係る回答前は、所得不明のため、所得を0円で算定しているためです。)
関連情報はこちら
- 非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について
倒産や解雇など非自発的な理由により、離職を余儀なくされた方の国保税を軽減する施策が、平成22年4月から実施されました。
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、ウェブリオまで問合せください。<外部リンク>