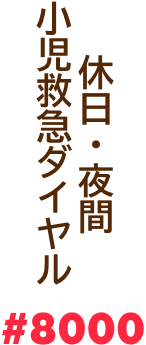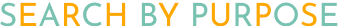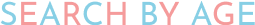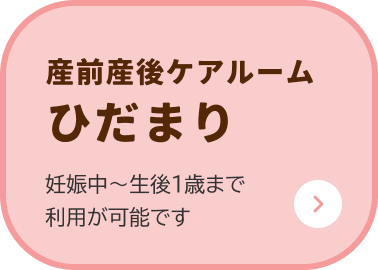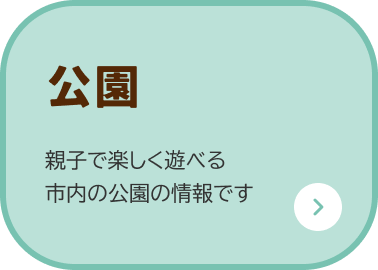本文
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度とは
病気やけがで通院や入院した場合、本人の負担した費用(保険適用分)を助成し、ひとり親家庭等※の精神的及び経済的負担を軽減し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
※ひとり親家庭とは、父母の離婚・死亡、父または母に一定の障害があること等により、父母のいずれか一方、または養育者が児童の看護をしている家庭(母子家庭、父子家庭、養育者家庭)のことをいいます。
助成対象となる方
- ひとり親家庭の父または母及び児童
- 配偶者のいない養育者及び児童
- 父母のいない児童
※対象期間は、児童が18歳に達した以後の最初の3月31日までです。
※児童の父または母が一定の障がいがある場合は対象になる可能性があります。
助成対象とならない方
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉施設又は障害者支援施設の入所者で医療費についてそれぞれの法律の定めるところにより支給されている方
- 小規模住居型児童養育事業を行う方または里親とそれに委託されている方
- 重度心身障害者医療制度により、医療費の助成を受けることができる方
助成条件について
保護者、児童ともに富士吉田市に住所があり、各医療保険に加入している方
申請者(父または母、養育者)が所得税非課税であること。但し、年少扶養親族に対する扶養控除の廃止及び16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分の廃止がないものとして計算した場合における所得税の額が0となる場合は対象となります。
※令和6年度分所得税につきましては、定額減税前の金額で審査を行います。
同居している扶養義務者がいる場合(住民票上の世帯とは関係なく、同所同地番に3親等内の直系血族(就労している児童を含む)、兄弟姉妹がいる場合)は、その扶養義務者の所得額が定められた所得制限額以下であること
新規申請について
助成を受けるためには申請が必要になります。必要書類を準備し、こども家庭センターまで提出してください。
必要書類
- ひとり親家庭医療費受給資格認定(更新)申請書
- 健康保険証の写し、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナ保険証の確認画面のうちいずれか(受給対象者全員分)
※健康保険証については、令和7年12月2日以降は確認書類として利用できません。
- 申請者名義の通帳等(金融機関がわかるもの)
- 戸籍謄本(児童扶養手当を受給中または申請中の方は省略可能)
※ひとり親家庭医療費助成の資格開始日は原則、申請日からになります。
各種届出が必要な場合
助成を受けている方は、資格内容に変更があった場合は届出が必要になります。
- 加入保険、住所、氏名等に変更があったとき
- 転出、婚姻(事実上の婚姻関係を含む)や生活保護の対象になったとき
- 養育している児童の人数が変わったとき
- 受給者証を紛失してしまったとき
- 同居する扶養義務者に増減があったとき
※受給資格がなくなった場合には、喪失の届出を提出し、受給者証を必ず返却ください。
助成の対象となる医療費
山梨県内での入院及び通院の保険診療一部負担金(自己負担分)を助成します。
ただし、次の給付等がある場合には、その額を対象経費から控除します。
- 国、県、市が負担して医療を給付するもの(育成医療、未熟児養育医療、小児慢性特定疾患治療など)
- 各種健康保険の保険者等が負担するもの(各種付加給付、高額療養制度にかかるものなど)
助成の対象とならない医療費
保険適用外の診療(診断書、差額ベッド代等)については自己負担となります。
交通事故などの第三者行為による診療の場合。
園や学校の管理下でのケガ等で、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度対象の場合、ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証は使用できませんので、一度自己負担していただき、園や学校に申請してください。
助成の方法1 窓口で医療費を支払わない場合(現物給付)
山梨県内の医療機関受診の場合(一部対象外の医療機関あり)
健康保険証(令和7年12月1日まで)、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナ保険証(受給対象者全員分)と、ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証(青色の証)の両方を医療機関窓口に提示することにより、自己負担なしで受診できます。
※受給者証の提示がない場合、受給者証の内容に相違がある場合には、窓口無料にはなりません。
助成の方法2 窓口で医療費を支払う場合(償還払い)
- 山梨県内の医療機関等の窓口で「ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証」を提示しない場合
- 山梨県内の医療機関で、現物給付対象外の医療機関等で受診した場合
- 山梨県外の医療機関受診の場合
- 補装具・治療用眼鏡等の場合
- 一部の国民健康保険組合に加入されている場合(山梨県医師国保、全国歯科医師国保、全国土木建築国保、中央建設国保を除く)
- 子の入院に伴う食事医療費(食事代) の場合※
※令和6年4月以降の入院分から助成の対象となりました。
医療費の自己負担分を医療機関の窓口でお支払いください。その後、下記の方法で申請をしてください。
医療費の申請方法
申請期間
受診日の翌月以降~2年間(例:令和7年4月受診分は、令和7年5月~令和9年4月末までが申請期間です)
持ち物
- ひとり親家庭医療費助成申請書(こども家庭センター窓口にあります。ホームページからもダウンロード可能です)
- 領収書(原本、コピー不可)
- 資格確認書類
(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナ保険証の確認画面のうちいずれか)
※健康保険証については、令和7年12月2日以降は確認書類として利用できません。
- ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証(青色の証)
- 保護者名義の通帳(既に登録してある口座以外に振り込む場合)
申請場所
こども家庭センター窓口(子育て支援センター1階)
助成金の支払
申請書を受付後、内容を審査し、申請の翌月20日(土、日、祝日の場合は翌営業日)に指定口座に振り込みます。
注意事項
申請書は、子ども一人につき「月ごと、医療機関ごと通院、入院ごと」に記入してください。
受給資格を喪失した方
婚姻(事実上の婚姻関係も含む)・転出等をされた場合は、ひとり親家庭等医療費助成の資格が喪失となりますので、受給者証の返却をお願いいたします。
こども家庭センターまでご連絡ください。
受給者証の再交付について
受給者証を紛失、破損した場合は速やかに再交付申請の届出をしてください。
再交付の際には保険証情報の確認を行いますので、資格確認書類(健康保険証の写し、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータル「健康保険証」の確認画面のうちいずれか)をご準備ください。
※健康保険証については、令和7年12月2日以降は確認書類として利用できません。
更新手続きに関して
ひとり親家庭医療費助成金受給資格者は毎年8月に受給者証の更新手続きが必要です。
該当者の方には毎年7月に、提出書類に関するご案内を送付します。8月中の指定された期間内に必ず提出をお願いします。
更新手続きが8月中に行われない場合、医療費の助成を受けられない期間が発生する可能性があるため、ご注意ください。
受給者証の有効期限は9月1日から8月31日及び児童が18歳に達した以後の最初の3月31日までとなります。