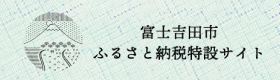本文
森林の伐採届制度
森林の立木を伐採する場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する必要があります(森林法第10条の8第1項、森林法施行規則第9条)。
また、主伐(間伐以外の伐採)を行う場合で、転用伐採を行う場合には「伐採に係る森林の状況報告書」を、伐採の後に造林を行う場合には「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を、それぞれ提出することが森林法で義務づけられています(法第10条の8第2項、規則第14条の2)。
1-1 伐採及び伐採後の造林の届出書
-
伐採届の提出日と伐採期間の始期は90日から30日空けること。
-
伐採する森林の所在する市町村ごとに提出すること。
-
届出人は、森林所有者(土地開発者または土地を借りて立木を所有する者)であること。法人である場合には、その名称及び代表者の氏名を記載すること。ただし、所有権の移転が確実である、また、移転はしているが未登記である等の事情があれば、新所有者によることができる。
-
伐採者と造林者が異なる場合は、両者の連名とすること。
-
伐採予定の全ての地番を記載すること。
1-2 伐採計画書
-
伐採面積欄には、haを単位として単位以下第3位を四捨五入し、小数第2位にとどめて記入する。また、面積が50平方メートル未満の場合で小数第2位に達しない場合は、第4位を四捨五入し、第3位まで記載すること。
-
伐採方法欄には、「主伐」又は「間伐」のどちらかを記載する。伐採跡地を森林以外の用途に供する場合(転用伐採)は、「主伐」とする。
-
主伐は、一般に伐採時期に達した成熟木を伐ること。
-
間伐は、森林を成熟させ主伐に至る過程において、生産の目標にあうよう立木の密度を調整するために行う伐採である。
-
主伐の場合、「皆伐」又は「択伐」のどちらかを記載する。
-
「皆伐」は、区域の立木を全部伐採すること。また、転用伐採は「皆伐」となる。
-
「択伐」は、大小老幼の樹木が混生している森林で、生産目標に達した立木を単木的に伐採すること。
-
-
伐採率欄には、立木材積による伐採率を記載することが望ましいが、難しい場合は、総立木本数に対して伐採しようとする立木本数の割合を目安として記載してもよい。
-
伐採齢欄には、伐採しようとする樹木の樹齢が各々異なっている場合には、上段に「最も多い年齢」、下段に「最も低い年齢~最も高い年齢」を「〇~〇」のように記載すること。
-
伐採の期間欄に記載された期間が、伐採届の有効期間である。提出済みの伐採届に記載されている森林であっても、その伐採期間を越えて伐採しようとする時は、改めて伐採届を提出することが必要である。また、同一地番での伐採の期間が1年を越える場合には、任意様式による年次計画を添付すること。
1-3 造林計画書
-
伐採後の造林の計画では、(1) 造林の方法別の造林面積等の計画欄と(2) 造林の方法別の造林の計画欄の該当箇所に記入すること。
-
造林期間は、伐採した日を含む年度の翌年度初日から起算して、それぞれ次の期間する。
人工造林:2年以内(皆伐)、5年以内(択伐)
天然更新:5年以内
但し、天然更新の場合で、5年後において的確な更新がなされない場合:5年を経過した日から2年以内
また、転用の場合で、5年後において転用が完了しなかった場合にも、2年以内の造林計画を記載 -
伐採跡地の造林の方法別は、人工造林(植栽、人工播種)、天然更新(ぼう芽更新、天然下種)の別に区分して記載する。
-
天然更新が計画されている場合には、天然更新補助作業が有無を記載(選択)すること。
-
ぼう芽更新の場合には、(2)の造林樹種には広葉樹のみ記載すること。
-
(2)の造林樹種、樹種別の植栽本数は富士吉田市森林整備計画に照らして適正なものとすること。
-
(2)の「作業委託先」の欄は、自ら行う場合は空欄で構わない。
-
天然更新及び転用の場合には、(2)の「5年後において的確な更新がなされていない場合」について記載しておくこと。
-
-
(3) 伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途欄には、伐採後において当該伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合にのみ、その供されることとなる用途(「住宅地」「農地」等)及び転用の時期を記載すること。
-
森林以外の用途に供する場合 届出個所の周囲で転用が行われている、またその予定がある場合、林地開発許可の対象となる場合があるので注意すること。
2 伐採届の添付書類について
-
位置図(森林の位置が特定できる図面)と区域図(公図など伐採する森林の外縁が明示された図面)
-
届出者の確認書類
個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類 -
土地登記事項証明書又は権利書等の写し(課税明細書も可)
-
伐採前の写真
3 森林の状況報告書について
伐採方法が「主伐」の場合には、森林の状況報告書を提出すること。状況報告書は、伐採及び伐採後の造林を完了した日からそれぞれ30日以内に提出すること。
-
伐採に係る森林の状況報告書
伐採後に森林以外の用途へ転用を行う場合に提出し、伐採後の森林の写真を添付すること。この場合、伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出は不要である。 -
伐採後の造林に係る森林の状況報告書
森林所有者が自ら造林をするときは森林所有者が、森林所有者以外の者が権限を有して行う場合は伐採後の造林を行う者が提出し、造林後の写真を添付すること。この場合、1の伐採に係る森林の状況報告書の提出は不要である。
4 伐採届Q&A
Q1 なぜ届出が必要なのか?
A 市町村森林整備計画に従った適切な施業をし、健全で豊かな森林を作ることができるよう、伐採及び伐採後の造林計画を届け出ることが義務付けられています。
Q2 どんなときでも届出は必要なのか?
A 法第5条に規定する都道府県知事がたてる地域森林計画の対象である森林については、原則として事前の届出が必要です。ただし、林地開発の許可を受けた森林を伐採する場合は届出の必要はありません。また、森林経営計画に基づいた伐採(法第10条の8第1項第4号)、緊急伐採(同項第9号)の場合は、事後の届出となります。
Q3 届出等をしない場合はどうなるのか?
A 伐採及び伐採後の造林の届出書:100万円以下の罰金(法第208条)
森林の状況報告書:30万円以下の罰金(法第210条)
Q4 合法性の証明になるのか?
A 伐採及び伐採後の造林の届出書及び適合通知書をクリーンウッド法における合法性の証明書類として活用できます。
Q5 届出の様式等は?
A 伐採及び伐採後の造林の届出書、森林の状況報告書などの様式及び記入例はこのページの下方にあります。また、富士吉田市役所西別館1階農林課にも備えてあります。
5 林地開発許可制度及び保安林の伐採について
伐採跡地の利用方法が森林以外の場合で、面積が1haを超える山林の開発および、太陽光発電設備の設置を目的とした土地の形質変更を行う場合で0.5haを超えるものについては、林地開発許可の対象となり山梨県知事の許可が必要となります。また、保安林の立木を伐採しようとする場合についても、山梨県知事の許可が必要となりますので、事前に富士・東部林務環境事務所にご相談ください。
問い合わせ先
【富士・東部林務環境事務所 森づくり推進課】
〒402-0054
住所 山梨県都留市田原2-13-43(南都留合同庁舎3階)
電話 0554-45-7812
PDFファイルはこちら
- 伐採届添付書類一覧 [PDFファイル/228KB]
- 1 伐採届記載要領・記載例(R5新様式) [PDFファイル/4.17MB]
- 2 伐採に係る森林の状況報告書記載要領・記載例(R5新様式) [PDFファイル/933KB]
- 3 伐採後の造林に係る森林の状況報告書記載要領・記載例(R5新様式) [PDFファイル/1.07MB]
- 4 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記載要領・記載例(H29-R4までの提出分) [PDFファイル/159KB]
ダウンロードファイルはこちら
- 1 伐採届(R5新様式) [Wordファイル/34KB]
- 2 伐採に係る森林の状況報告書(R5新様式) [Wordファイル/25KB]
- 3 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(R5新様式) [Wordファイル/25KB]
- 4 伐採及び伐採後の造林の状況報告書(H29-R4までの提出分) [Wordファイル/16KB]
リンクはこちら
- 林野庁:伐採及び伐採後の造林届出制度<外部リンク>
- 林野庁:保安林制度・林地開発許可制度<外部リンク>
- 山梨県:保安林制度<外部リンク>
- 山梨県:林地開発許可制度の手引き<外部リンク>
- 用語の解説<外部リンク>