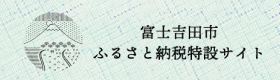本文
裁判員制度
裁判員制度とは
平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、平成21年5月21日から裁判員制度が始まりました。
この裁判員制度とは、国民のみなさんが、裁判員として刑事裁判に参加して、被告人が有罪かどうか、また、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度です。
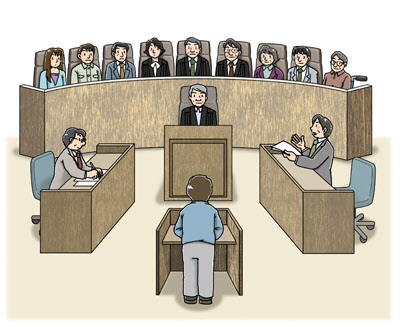
裁判員の選ばれ方
裁判員の選任は、前年の秋頃に地方裁判所ごとに、管内の市町村の選挙管理委員会がくじで選定した名簿に基づき、翌年の裁判員候補者名簿を作成します。
その後、裁判員候補者名簿に登載された方には、12月頃までに地方裁判所から名簿に記載された旨の通知があります。就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかどうかなどを尋ねる調査票も同封して送付されます。
該当する裁判が発生した場合、裁判所では、事件ごとに、裁判員候補者名簿の中から、くじにより裁判員候補者が選ばれます。
選ばれた裁判員候補者には、原則裁判の6週間前までに選任手続期日のお知らせ(呼出状)が質問票とともに送付されます。
事件概要の説明、当日用質問票の記入を経て、辞退希望の有無・理由や不公平な裁判をするおそれの有無などについての裁判長による質問手続により、選任・不選任が決定されます。
裁判員の仕事や役割
裁判員に選ばれたら、裁判官と一緒に、刑事事件の法廷に立ち会い、判決まで関与することになります。
公判では,証拠書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われます。裁判員から、証人等に質問することもできます。
証拠を全て調べたら、事実を認定し、被告人が有罪か無罪か、また、有罪だとしたらどんな刑にするべきかを裁判官と一緒に議論し(評議)、決定する(評決)ことになります。
評議を尽くしても、意見の全員一致が得られなかったとき、評決は、多数決により行われます。
評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決を宣告することになります。裁判員としての役割は、判決の宣告により終了します。
Q&A 裁判員になるための資格は?
衆議院議員の選挙権を有する方(20歳以上)であれば、原則として,誰でもなることができます(裁判員法13条)。
ただし、裁判員になることができない条件があります。
Q&A裁判員になることを辞退できる?
裁判員制度は、特定の職業や立場の人に偏らず、広く国民の皆さんに参加してもらう制度ですので、原則として辞退できません。
ただし、国民の皆さんの負担が過重なものとならないようにとの配慮などから、法律や政令で辞退事由を定めており、裁判所からそのような事情にあたると認められれば辞退することができます。
裁判員制度について詳しくはこちらを<外部リンク>