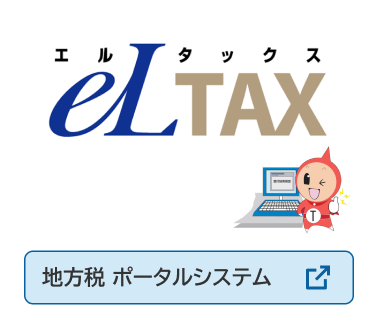本文
事業主の皆さんへ 個人住民税特別徴収の実施と納入
- 個人住民税の特別徴収とは、事業主の皆さまが国の所得税と同様に特別徴収義務者として、納税義務者に支払う給与から毎月徴収し、納税義務者の住所地の市町村に納入していただく制度です。
- 地方税法第321条の4及び各市町村の条例により、給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収により納めていただくことになっています
事業主(給与支払者)には個人住民税の特別徴収義務があります。
事業主(給与支払者)は、地方税法及び各市町村の条例により個人住民税の特別徴収義務者として指定されています。
特別徴収義務者は、個人住民税の納税義務者である従業員の給与から、毎月個人住民税を特別徴収(引き落とし)して、従業員の住所地市町村へ納入する義務を負っています。
特別徴収制度は従業員にとってたいへん便利な制度です。
個人住民税の特別徴収制度は、「従業員が個々に納税のため金融機関に行く手間が省ける」「住民税の納め忘れにより滞納となったり、延滞金が発生する心配がない」など、納税義務者である従業員にとってたいへん便利な制度です。
また、従業員が自分で納付する普通徴収が原則として年4回払いであるのに対し、特別徴収は年12回払いになるので、納税に係る従業員の1回当たりの負担が少なくてすみます。
一定規模以上の事業所から順次個人住民税の税額決定通知をお送りします。
所得税と違い税額計算は市町村で行い、平成23年5月中旬に従業員ごとの特別徴収税額を通知しますので、この通知に記載された金額を、平成23年6月以降にそれぞれの従業員の給与から毎月特別徴収(引き落とし)してください。
特別徴収した税額は、翌月10日までに該当市町村に納入していただくことになります。
特別徴収(引き落とし)していなくても事業所には従業員の個人住民税の納入義務があります。
事業主(給与支払者)は、特別徴収税額の決定通知があった場合、特別徴収しなかったとしてもこの税額の納入を拒否することはできません。
このため、納入がない場合は給与支払者である事業主(特別徴収義務者)に対し滞納処分を行うことにより徴収することとなります。(特別徴収義務者と納税義務者である従業員との間で民法上の求償権は生じます。)
すべての従業員から特別徴収(引き落とし)することが必要です。
特別徴収制度は法令で規定されており、事業主(給与支払者)や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。
現在特別徴収となっていない従業員には、特別徴収への切り替えが必要であることを説明してください。
ただし、次のような従業員からは特別徴収できません。(具体的には給与支払報告書を区別して提出していただくことになります。)
【例】
- 他から支給される給料から個人住民税が引かれている。
- 一時的な雇用で、翌年の給与から引き落としが不可能である。
- 給与に毎月支給額が少なく、個人住民税を引き落とししきれない。
- 給与が毎月支給されない。
従業員の異動があったときはお知らせください。
従業員の方が年度の途中で退職・休職等をされて、給与から引き落としができなくなった場合は、速やかに所定の異動届書を当該市町村へ提出してください。該当市町村から特別徴収税額の変更通知書をお送りします。
特別徴収事務の手続き
- 平成23年1月
給与支払報告書を従業員の住所地市町村に提出する際、総括表に特別徴収と記載してください。 - 平成23年5月中旬
特別徴収を行う従業員の所在地のある市町村から貴事業所に、特別徴収税額の決定通知書(事業所用、納税義務者用)、納付書などを送付しますので(税額の決定通知書(納税義務者用)は、該当従業員に配布していただきます。)、給与の支払いを受けている納税義務者に対して通知してください。 - 平成23年6月
6月分給料日から引き落としを開始します。(翌年5月まで毎月) - 平成23年7月10日
6月分として引き落としされた住民税は、翌月10日までに、所定の納付書によって、金融機関等から該当市町村に納入していただきます。7月分以降も同様です。
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、ウェブリオまで問合せください。<外部リンク>