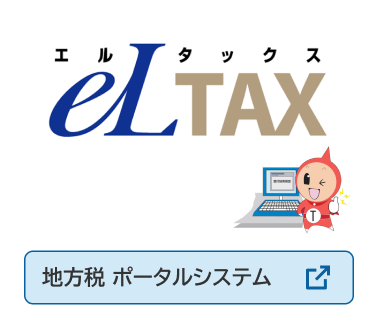本文
納税に関する質問箱
よくある質問にお答えします
Q1.財産の差押をされないためにはどうすればよいですか?
延滞金を含め、滞納税額を完納すれば差押えになりません。
Q2.毎月分割で納付しているので差押はされませんよね?
分割納付中であっても、早期に完納の見込みが無い場合、本人所有の資産が発見された場合等、そのまま分割を続けることが適当でないと認められる場合は差押を行う場合があります。
Q3.借金やローンがあるので税金を払えません
法律によって税金はすべての債務(借金含む)に優先すると定めてあります。個人債務より税金が優先されます。
借金やローンは滞納の理由にはなりませんし、考慮されません。
ですので、借金やローンの返済の前に税金を納めて下さい。
※担保の目的物が差し押さえられた場合、期限の利益を喪失し債務の一括弁済を求められる場合があります。
Q4.いきなり財産を差し押さえたという通知が届きました。事前に本人に連絡して同意を得る必要がありませんか?
税は納期内納付が大原則です。「督促状発送日から10日を経過したときは差し押さえをしなければならない」と法律に明示してあります。
このことから事前の連絡や本人の同意なしに差し押さえをすることができ、差し押えた後に書面で通知しています。
また、納期限から20日以内に「督促状」を送付し、その中に滞納処分について記載されています。いきなりではありません。
なお、差押は滞納者の実態を把握してからでないとできませんので、納期限が過ぎて相当時間が経ってから執行される場合もあります。
Q5.納期限を過ぎてから納付したら延滞金の納付書が送られてきました、どうしてですか?
納期限を過ぎると法律で決められた割合で毎日延滞金が加算されていきます。これは、納期限までに納めた方との公平性を保つためです。
延滞金も納付されないと税金と同じように差押等の滞納処分の対象となります。
Q6.以前に担当者が延滞金をまけてくれると約束したのにできないと言われた
担当者がそういった発言をすることはないはずですが、たとえ言ったとしても担当者に延滞金を減額する権限はありませんので、延滞金が減額されることはありません。
最高裁の判例でも、このような場合には信義誠実の原則の適用はないとされています。最高裁判決(昭和62年10月30日判決・集民152号93頁)によると租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法関係において、禁反言の法理の適用は慎重でなければならないとしています。
Q7.納税通知書や督促状が届いていないのに滞納処分を受けたのはおかしい
他の郵便物に紛れていないかなど、もう一度ご確認下さい。
法律により、一般の郵便で税金に関する書類を送付し、返戻がなかった場合、行政機関に送付記録があれば「通常到達すべきであった時」にその書類が届いたと推定されます。
これは「送った」「届いていない」という水掛け論を防ぐとともに、悪意のある納税者を排除するためです。
また、税金は通知が届いてから納期限までに納めるのが原則です。しかし納税は国民の義務ですので、納税者の側も『自分がいつ、何の税金を納めなければならない』というのを自覚していなければなりません。
実際に「○○税の通知が来る時期だと思うがまだ届いていない」と連絡をしてくる納税者の方もいます。
それに対し「本当に届いていない」と主張するためには納税者側で郵便事故等によって届いていないということを証明する必要があります。
Q8.差し押さえられるのは滞納者本人名義の財産だけですよね?
他人名義の財産であっても滞納者の財産と認定し差し押さえることができる場合があります。
例えば
- 妻が夫の給料等の所得を管理し、妻名義で預金している場合
- 夫が妻名義の預金で事業の収入支出を行っているような場合
というようなケースでは妻名義の預金であっても夫(滞納者)の預金であると認定して差し押さえをすることができます。
Q9.市税を納めすぎてしまったので還付されるはずでしたが、何の連絡もなく未納の税金に充当されました、どうしてですか?
納めすぎた税金を還付する場合に、未納の税金があるときは、法律によりその還付金を未納の税金に充当しなければならないと定められています。また、充当した場合には、その旨を納税義務者等に通知することになっています。
Q10.差押は裁判所に申し立てなければできないのでは?
行政機関は租税等を自ら強制徴収することができます。これを自力執行権といいます。
租税・公課は一般の私債権とは異なる性質を有しており、その徴収確保(財政基盤の確保)は市の責務であるためです。
Q11.滞納処分の内容に疑問や不服がある場合はどのようにすればよいですか?
滞納処分などの内容に疑問がある場合は、収税課までお問い合わせください。
滞納処分の内容に不服があるときは、市長に対して「審査請求」をすることができます。
| 審査請求をすることができる期間 | 原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内 |
|---|---|
| 審査請求の方法 | 必要事項を記載し押印した審査請求書を市役所に提出してください |
| 審査請求書の記載事項(必須) |
|
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、ウェブリオまで問合せ<外部リンク>ください。